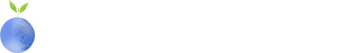不用品片づけ神奈川.COMでは、一般個人宅の不用品片付けから、オフィスや店舗・事業所の撤去まで、お客様の多様なニーズにお応えします。神奈川県をはじめ、東京都・埼玉県・千葉県での出張作業に対応。片付けと同時に買取も行っており、製造から3年以内の家電や家具は特に高価買取しております。まずはお気軽に無料見積りをご依頼ください。
新型コロナウイルス感染症予防に対する弊社の取り組みについて
- 出社従業員全員の体温・体調を確認しております。
- アルコール消毒・手洗い・うがいを徹底しております。
- マスクを着用して対応させて頂きます。
最短即日!スピード対応でお急ぎの方も安心!
お客様のあらゆるニーズにお応えするため、最短で即日対応も可能です。急な引っ越しで「明日までに部屋を片付けたい」という方もお気軽にご相談ください。首都圏全域にトラックが巡回しているため、スピーディーに訪問日程をご案内することができます。

他店より2割から5割も安い!驚きの低価格!
独自の再販ルートを確保することにより、一般的な片付け業者よりも2割〜5割も安い費用を実現しています。商品の状態によっては買取も可能なため、片付け費用を相殺することでさらに安くなるケースも! まずはお気軽に無料見積もりをお申し込みください。

経験豊富な専門スタッフが親切・丁寧に対応!
お客様の安心・満足を第一に考え、親切・丁寧な対応をモットーとしています。電話対応するオペレーター・現場で作業するスタッフは、社内で厳しい教育を受け豊富な経験を積んだプロスタッフです。安心してお任せください。

無料見積りのご依頼
無料見積もりフォームまたはお電話より、無料見積もりをご依頼ください。
料金案内・日程調整
お客様のご希望をもとに、訪問日時を決定いたします。
訪問・お品物確認
ステップ2で決定した日時にお客様宅へお伺いし、お見積もり金額をご案内します。
片付け作業
お見積もりに了承いただけましたら、片付け作業に移らせていただきます。
お支払い
作業後、お部屋を確認いただき、問題なければ料金をお支払いいただいます。
実際に当店をご利用いただいたお客様の『喜びの声』をご覧ください。
半分以上が買取や
リユースの対象に!
神奈川県横浜市神奈川区
20代 女性
引越することになり当初は全て処分になるものと考えていましたが、半分以上が買い取りやリユースの対象になり、とても助かりました。また何かあったら宜しくお願い致します。
急な依頼にも快く
対応してもらえた!
神奈川県相模原市
50代 男性
急な依頼をだしましたが、快く対応していただけました。すぐ対応出来ない場合も色々な代替案を提示して貰えた(別の日取りや、店舗への直接持ち込みなど)ので誠意を感じました。
2、3日内で倉庫が
片付き助かりました!
神奈川県藤沢市
40代 男性
すぐに営業の方が来て見積りしていただきました。金額も納得の金額だったのですぐに依頼したところ2、3日内で片付けてくれました。本当に助かりました。

見積もり後、キャンセルしても大丈夫ですか?
はい。お見積り金額に納得いただけない場合はキャンセルも可能です。その場合も費用は一切かかりませんので、安心してご依頼ください。
作業を行う日時を指定することはできますか?
日時のご希望はお気軽にお申し付けください。トラックとスタッフの空き状況にもよりますが、できるだけご希望にお応えします。
昼間忙しいので、夜間に来てほしいのですが…?
18時から21時の間でしたら、夜間指定オプションで作業が可能です。オプション料金として4,000円(税別)をいただきます。どのようなご要望も遠慮なくお申し付けください。
近所に知られないように作業してほしいのですが…?
熟練のスタッフが迅速に作業いたしますので、ご近所に気づかれずに作業を終えることができます。お客様の秘密は厳守いたしますので、ご安心ください。
クレジットカード払いは利用できますか?
お支払い金額が3万円以上の場合は、クレジットカード払いがご利用いただけます。

神奈川県
川崎市(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区・相模原市・緑区・中央区・南区)・横浜市(鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区)・相模原市・三浦市・横須賀市・逗子市・鎌倉市・藤沢市・茅ヶ崎市・葉山市・大和市・綾瀬市・海老名市・座間市・平塚市・伊勢原市・厚木市・秦野市・小田原市・南足柄市・箱根市・湯河原市
以下のエリアも対応いたします!
東京都
東京都港区・千代田区・中央区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・ 渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・立川市・あきる野市・武蔵村山・青梅市・日野市など(一部地域を除く)
埼玉県
さいたま市・戸田市・坂戸市・川越市・所沢市・狭山市・蕨市・入間市・八潮市・和光市・草加市・三郷市・志木市・春日部市・上尾市・松伏町・新座市・朝霞 市・川口市(鳩ヶ谷市)・越谷市・ふじみ野市・吉川市・深谷市・桶川市・熊谷市・鴻巣市・東松山市・久喜市・加須市・羽生市など(一部地域を除く)
千葉県
千葉県千葉市(美浜区・花見川区・稲毛区・若葉区)・館山市・南房総市・鴨川市・富津市・君津市・勝浦市・いすみ市・木更津市・袖ヶ浦市・市原市・茂原市・ 東金市・山武市・匝瑳市・旭市・銚子市・八街市・香取市・成田市・佐倉市・四街道市・印西市・八千代市・習志野市・船橋市・白井市・我孫子市・柏市・松戸市・市川市・浦安市・鎌ヶ谷市・流山市・野田市など(一部地域を除く)
お問い合わせは「個人情報保護方針」をお読みの上、こちらのフォームからお願いいたします。
通常、24時間以内の回答を心がけております。片付けのご依頼は、無料お見積りフォームをご利用ください。
お急ぎのお客さまは下記フリーダイヤルにお願いします。
TEL:0120-997-836
対応時間:AM 9:00~PM 6:00
※は必須項目です。必ずご記入ください。
「お問い合わせにおける個人情報の取扱いについて」
(1)事業者の氏名または名称
株式会社エコアース
(2)個人情報の利用目的
お問い合わせいただいた内容に回答するため。
(3)個人情報の第三者提供について
取得した個人情報は法令等による場合を除いて第三者に提供することはありません。
(4)個人情報の取扱いの委託について
取得した個人情報の取扱いの全部又は、一部を委託することはありません。
(5)個人情報を与えなかった場合に生じる結果
個人情報を与えることは任意です。個人情報に関する情報の一部をご提供いただけない場合は、お問い合わせ内容に回答できない可能性があります。
(6)開示対象個人情報の開示等および問い合わせ窓口について
ご本人からの求めにより、当社が保有する開示対象個人情報に関する開示、利用目的の通知、内容の訂正・追加または削除、利用停止、消去および第三者提供の停止(以下、開示等という)に応じます。開示等に応ずる窓口は、下記「当社の個人情報の取扱いに関する苦情、相談等の問合せ先」を参照してください。
(7)本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
クッキーやウェブビーコン等を用いるなどして、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。
(8)個人情報の安全管理措置について
取得した個人情報については、漏洩、減失またはき損の防止と是正、その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。お問合せへの回答後、取得した個人情報は当社内において削除致します。
(9)個人情報保護方針
当社ホームページの個人情報保護方針をご覧下さい。
(10)当社の個人情報の取扱いに関する苦情、相談等の問合せ先
窓口の名称 「個人情報苦情相談問合せ窓口」
【連絡先】
担当者 : 山田 達也
住所 : 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川6-14-10
電話 : 0466-86-8717
FAX : 0466-20-1120
メール : info@ecoecoearth.net